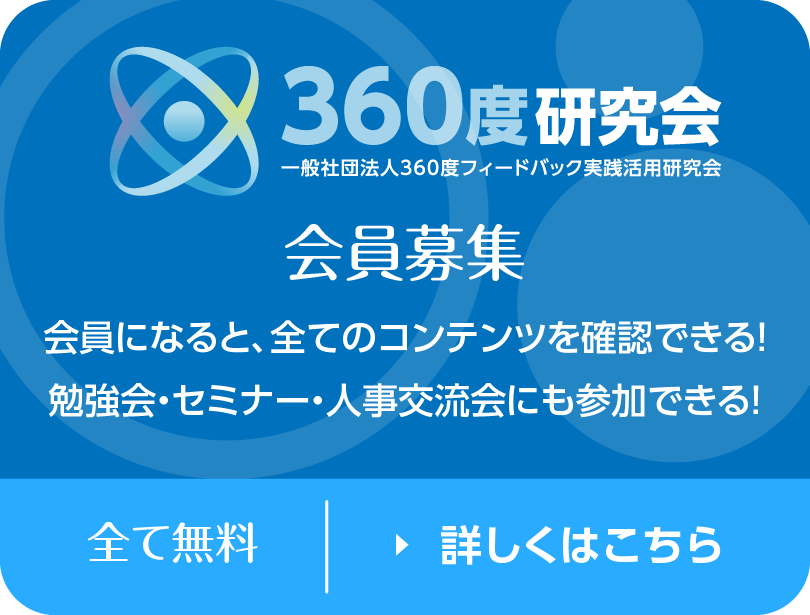-1200x675.jpg)
定量と定性 2種類の設問によって構成
「設定した行動に対して段階回答させる定量的設問(段階回答設問。リッカート尺度)」と「思ったことを自由に記述させる定性的設問(フリーコメント設問)」があります。
フリーコメント設問には、対象者の「良い点」「改善点」を回答させるのが一般的ですが、設問に様々な工夫を講じることで、対象者にとって役立つ内容を引き出すことができます。
段階回答設問は、実施目的にあわせた内容とすることが大原則です。
「期待する人材像」「経営として改善すべき組織課題」などを踏まえ、対象者にとって気づきや行動変容につながる内容を検討すべきです。設問をいかに設計するのかによって、360度フィードバックの実施効果は大きく変わってきます。
できれば、外部業者が提供している汎用設問を安易に使用するのではなく、自社としての意志や課題意識を持ってオリジナル設問を設計することが望ましいと言えます。
「回答段階設問」は何問くらい設定するの?
20~30問程度の設問を設定するのが一般的です。
設問数が少なすぎると複数の設問に多くの意味を盛り込み過ぎてしまい、回答も曖昧になります。
逆に、設問数が多すぎるとサーベイ回答の負荷が増大し、適当に回答する人が増える傾向があります。
何よりも本人にフィードバックした際に、解釈すべき情報が多すぎて大事なポイントがぼやけてしまうことがデメリットとして考えられます。
深く考えるべき「回答段階」と「回答基準」
段階回答設問における回答尺度を何段階に設定するのかについても検討する必要があります。
必ずしも正解があるわけではありませんが、一般的には5段階での回答が多いと言えます。
5段階の場合、以下のような回答基準が設定されます。(あくまで一例です)
【例】5:極めて高いレベルでできている 4:できている 3:どちらかといえばできている 2:どちらかといえばできていない 1:できていない
【例】5:できている 4:どちらかといえばできている 3:どちらともいえない 2:どちらかといえばできていない 1:できていない
ここで考えるべき大事なポイントは、3段階目に「どちらともいえない」という中間尺度を設定するかどうかということです。
このことについては、様々な考え方がありますが、「どちらともいえない」は安易に選択されやすく、中心化傾向が生じやすくなると言えます。
また回答者によって、対象者の全ての行動までは観察困難なケースも想定されるため、設問ごとに「わからない(NA:No Answer)」という回答基準を設定しておくことをおすすめします。
なお、「わからない」という回答があった場合、集計対象から除外します。
意外と奥深く効果に影響する「フリーコメント設問」
「フリーコメント設問」は、“対象者の強み(良い点)と弱み(改善点)を自由記述させるもの”と安易に考えがちですが、具体的な聞き方(設問表現)や様々な工夫によって多くの情報や本音を回答させることもできます。
この工夫は対象者への気づきや動機づけにも大きな影響を与えることができます。
とはいえ、工夫している会社は意外と少ないと言えます。設問表現を見直すだけのちょっとした工夫であるだけに、とてももったいない状況になっています。
対象者は、回答されたフリーコメント内容を確認することで、段階回答設問だけでは理解が難しかった自分の現状を振り返ることができます。
そのために、できるだけ具体的、そして本音のコメントを記入させる工夫が重要です。
ご興味ある方は、【個別無料相談】経由でご連絡ください。