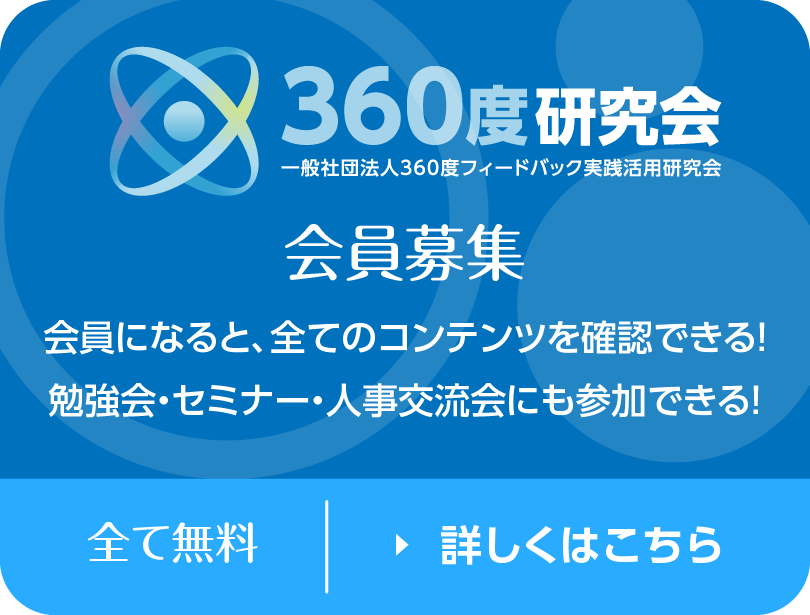-1200x675.jpg)
人事部としての「結果分析」 しかし、安易に考えると誤った解釈のリスクあり
360度フィードバックは、対象者個々人に返却して「気づき」「人材育成」「組織づくり」に効果を発揮します。それに加え、人事部として実施結果を集計分析することで、今後の人事施策に向けて有益な情報として活用することができます。
例えば、「階層別、部門別、職種別の強みや弱みの把握 ⇒ 組織課題の発見」「今後の人材育成施策の立案における参考情報」「昇進昇格、異動配置における参考情報」などです。
ただし、分析結果の解釈には要注意です。
360度フィードバックは、部門や職種によって有利不利が生じる特徴があります。また、実施プロセス(目的の打ち出し方など)や企業風土、業種など様々な要因によって結果の特徴や高低レベルは変わってきます。そのことを理解した上で結果を解釈しなければなりません。安易に結果数値を他社や他部門と比較することで、実態とは乖離した誤った解釈になってしまうことも少なくありません。ここには結果解釈の力量が求められるところです。
なお、個人結果を一覧化して人事評価(昇進昇格、異動配置など)として活用する場合は、特に考慮すべきことがあります。個人結果は、様々な外部要因によって他者回答値が変動します。それだけに、個人結果を回答値の高低によって安易に判断すると、不適切な人事にもなりかねません。
【個別無料相談】経由でご連絡いただければ、分析時や結果解釈における留意点、個人結果の扱い方など重要事項を解説いたします。
お勧めしたい「次回に向けての振り返り」
360度フィードバックは1回実施して終わりではなく、定期的に実施することで多くの対象者の行動変容につながっていきます。実際に多くの会社が定期的に継続実施されており、最も多いのは毎年1回のペース(頻度)での実施と言えます。
それだけに、初回実施、または本年度の実施が終了した後(例えば、個人報告書を対象者全員に返却した後)、次のことを行っておくことをお勧めします。
・本年度の実施結果の分析によって、どのような課題を設定したのか?
・その課題を解決するために、どのような施策を実行したのか?
・その施策によって、対象者に行動変容は見られたのか? (対象者全員でなくても、気になる対象者だけでも構わない)
・その行動変容は具体的にどのようなものであり、それによって対象者の組織に何らかの変化が生じたか?
などを整理しておくと、次回の実施においてより効果的な工夫を講じることができます。
「設問は同じままでよいのか? 設問の修正や追加などは必要ないか?」「フィードバック研修のプログラムにどのような工夫を講じればよいか?」など、間違いなく実施効果は高まっていくでしょう。
実施した施策を振り返ることは、当たり前のことかもしれませんが、きちんとできていない会社が多いと言えます。説明会やフィードバック研修後に受講者アンケートをとり、一定の満足度があればそれで成功としている会社もありますが、それでは不十分と言えます。