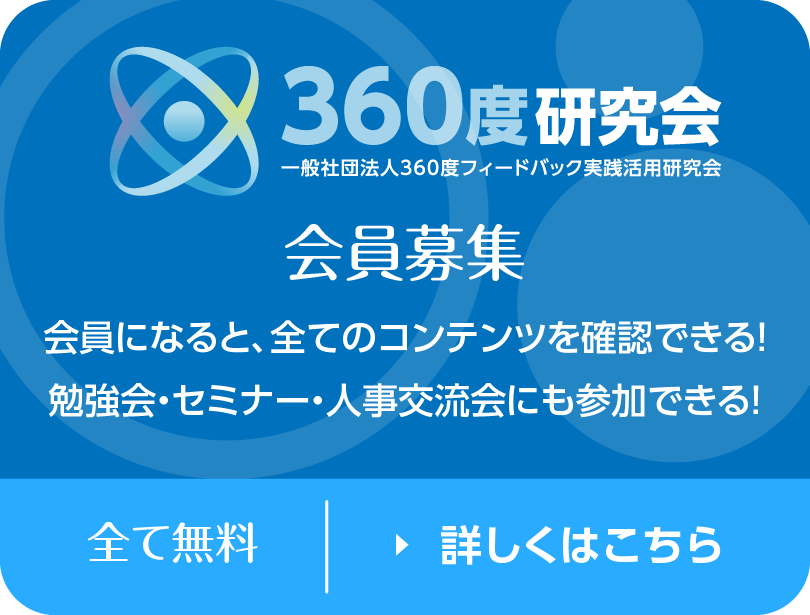多くの企業が毎年1回、360度フィードバックを導入しています。
ところが、「結果が昨年とほとんど変わらない」「数年続けても期待したような向上が見られない」といった声は少なくありません。人事担当者からは「せっかく多くの手間とコストを掛けて実施しているのに…」という嘆きもよく耳にします。
これは360度フィードバックという仕組み自体の限界なのでしょうか?
実はそうではありません。多くの場合、「気づき → 改善行動 → 継続」というプロセスのどこかで“つまずき”が起きているのです。
1.「気づき」が表面的に終わる
360度フィードバックの本質は、他者の視点を通じて自己理解を深めることです。
しかし実際には「思っていた通りだった」「なるほどな」といった軽い感想で終わり、深い内省に至らないケースが多々あります。
表面的な気づきに陥る典型パターン
1)納得済み型
「自分でも薄々わかっていた」と受け流してしまい、改善行動につなげようとする
意識が薄く、そのまま放置してしまう。本人は納得しているつもりで満足してしま
っており、残念な状態です。
2)他責型
「この結果は私のことを嫌っている部下が反発して組織を乱しているからだ」と
外的要因に理由を求め、自分の改善点に正面から向き合わない。特にベテランの
管理職ほど自己防衛的に解釈する傾向があります。
3)早合点型
例えば、コミュニケーション上に問題がありそうだと感じれば、結果をざっと
眺めるだけで結論づけてしまう。
「要は自分は発信不足なんだな」と短絡的に解釈してしまうケースです。実際には
「発信不足」ではなく、「傾聴不足」であることが問題なのですが、本人には
その自覚はありません . . . . .
続きは、会員専用サイトにてご確認ください。