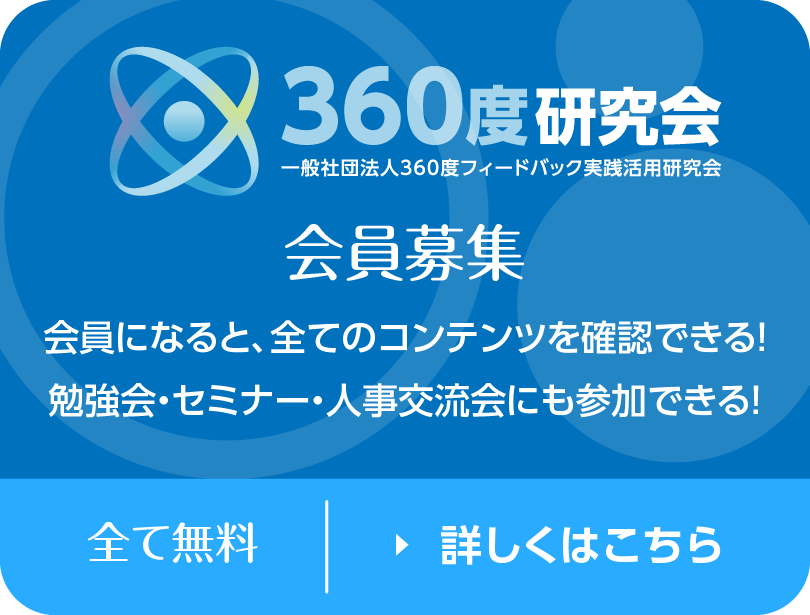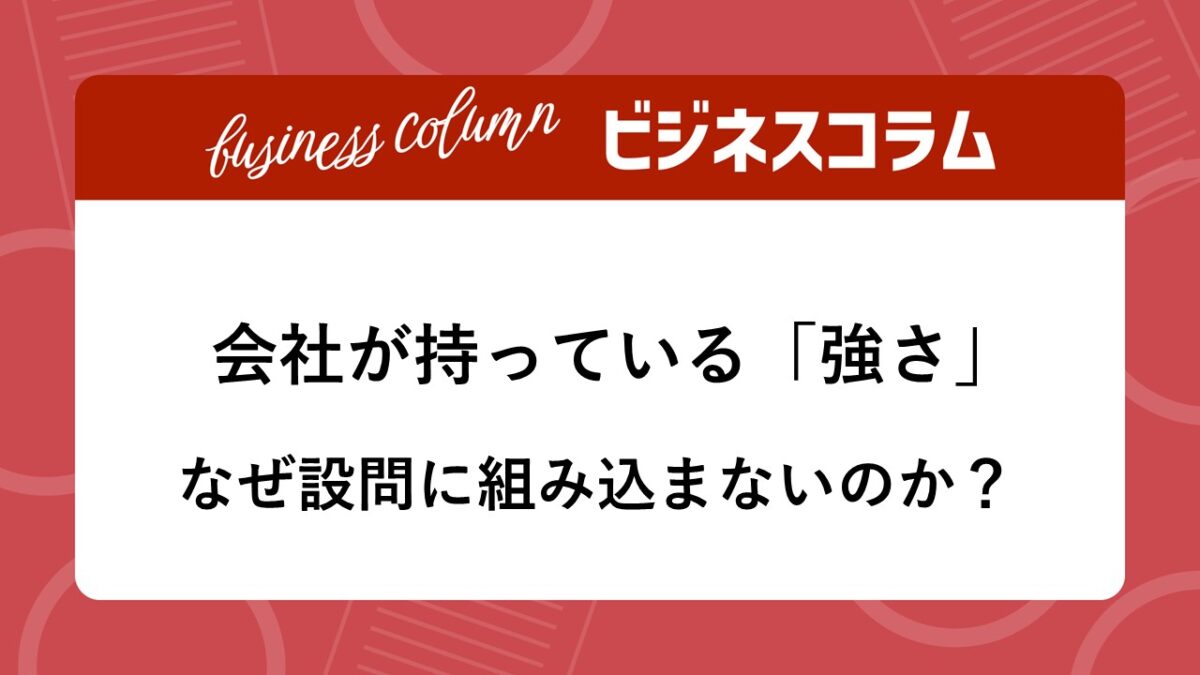
多くの企業が、自社の理想とするリーダー像を定義し、その行動特性を「コンピテンシー」などの形で言語化しています。それらは、高い成果を上げ続けるハイパフォーマーたちの行動特性を分析し、組織全体のパフォーマンスを引き上げるための、いわば「自社人材が活躍するための虎の巻」です。
しかしこの虎の巻は、しばしば「絵に描いた餅」となり、現場のマネジメントに何の変化ももたらさないまま、形骸化してしまうケースが後を絶ちません。
優れたリーダーは、ビジョンを熱く語り、逆境でもチームを鼓舞し、問題が発生すれば自ら矢面に立ちます。部下の小さな成功を共に喜び、日々の地道なコミュニケーションを怠りません。こうした理想の行動は誰もが理解しているはずなのに、なぜ多くの管理職はそれを実践できないのでしょうか。
その根源には、根深い「自己認識のバイアス」が存在します。
多くの管理職は「自分はできているつもり」「部下には伝わっているはずだ」と考えており、自身の行動が周囲に与える影響を客観的に把握できていないのです。
この「主観」と「客観」の間に横たわる深い溝こそが、リーダーの成長を阻み、コンピテンシーの浸透を妨げる最大の壁となっています。この壁を、いかにして打ち破るか。その鍵は、客観的な「鏡」を組織に導入することにあります。
成否を分けるポイント:「魂」の宿った設問設計
この「認識の壁」を打ち破るために、360度フィードバックは極めて有効なツールです。
上司、同僚、部下といった多角的な視点から得られるフィードバックは、管理職本人にとって、自身の行動を客観的に映し出す「鏡」の役割を果たします。
しかし、その効果を最大化できるか否かの鍵の1つになっているのが「設問設計」です。
360度フィードバックの導入を検討する際、一般的なテンプレート設問を用いる企業は少なくありません。しかし、それは既製服のようなもので、誰にでも当てはまる代わりに、心には深く響きません。そこには、自社の想いがないのです。
真に組織を変革する力を秘めているのは、自社の人材に対する期待がこもった設問であり、その一つに冒頭に記したコンピテンシーを埋め込んだ、自社向けオーダーメイドの設問です。
ある金融機関A社では、何年も前から360度フィードバックを継続的に実施していました。
初回実施では、「多くの気づき」を対象者に与えることができ、360度フィードバックという手法を高く評価していました。
しかし、意識の高い人事課長は、根本的なことを考えていました。
「そもそも気づきとは、何に気づかせるものなのか?」
「本人と他者の回答値のギャップに気づかせるだけで本当に良いのだろうか?」
「会社の業績向上につなげるためには、何に気づかせることが必要なのだろうか?」
そこで、高業績を上げ続ける支店長の行動特性を徹底的に分析し、独自のコンピテンシーを策定しました。そして、そのコンピテンシー項目を、具体的な行動レベルにまで落とし込んだ設問を作成し、従来の設問に置き換えて360度フィードバックを実施したのです。
例えば、「目標達成への意欲」という抽象的なコンピテンシーは、 . . . .
続きは、会員専用サイトにてご確認ください。