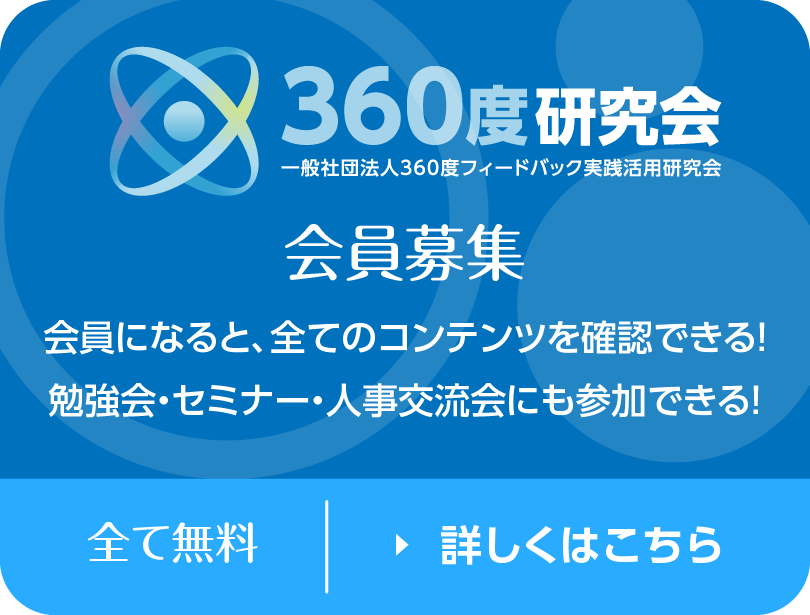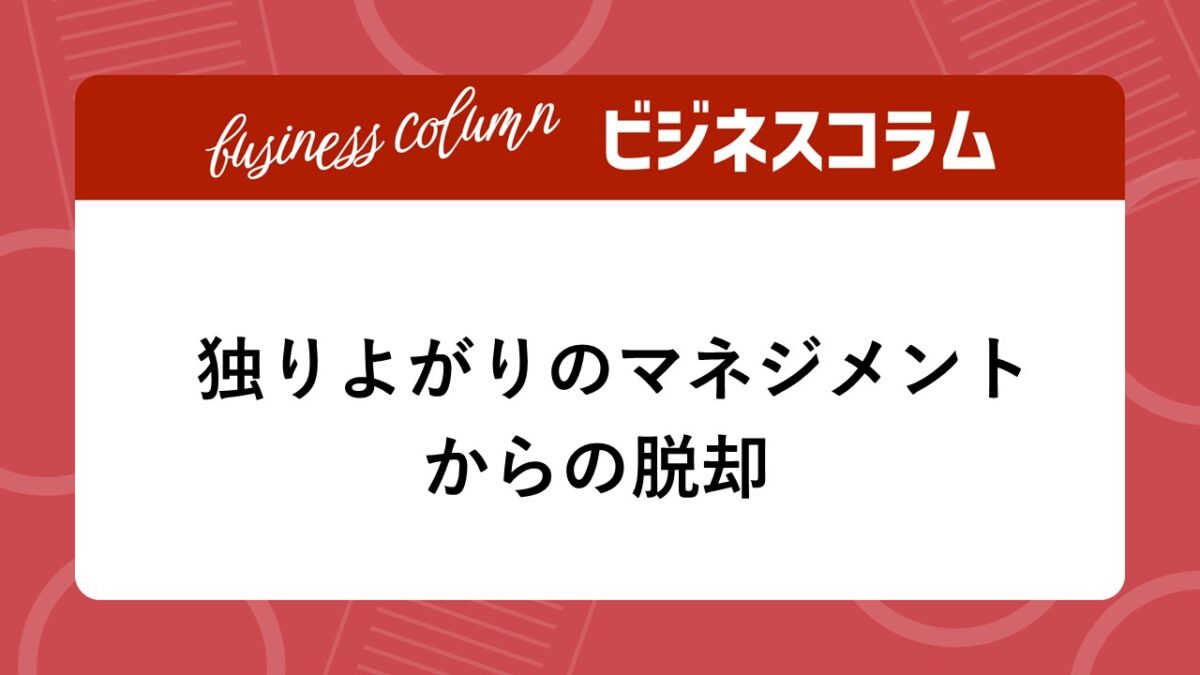
「俺が若い頃は…」という、善意の過ち
「私が若い頃は、上司に何かといえば怒鳴られ、提出資料を何度も突き返され、時には目の前でゴミ箱に捨てられるような環境で鍛えられた。だから、部下の成長を思えば厳しく接するのが愛情だ」
研修や面談で、今でもこうした“武勇伝”を語る管理職を時々見かけます。そこには部下を思う真剣な気持ちが込められており、決して悪意はありません。
しかし、その「良かれと思って」のやり方は、現代の職場では部下の心を傷つけ、組織全体の活力を奪ってしまうでしょう。
管理職にとっての成功体験が、若手にとってはプレッシャーや否定として届く...
このすれ違いは、実際に多くの職場で起きています。
「良かれ」が招く静かな離反
厳しい指摘で奮起を促すやり方は、かつては通用したかもしれません。
しかしハーバード・ビジネス・レビューに掲載された研究によると、人は批判的なフィードバックを受けると、その評価者から心理的にも物理的にも距離を置く傾向があるといいます。
若手社員の立場で考えてみましょう。
厳しい言葉が続くと、
「なぜここまで言われなければならないのか」
「何かといえば粗探しばかりで、良い点は全く見てもらえていない」
といった思いが募ります。
こうした疑念はやがて不信感に変わり、やる気を削ぎ、自己肯定感を下げます。
恐ろしいのは、この離反が表面化せず、静かに進行することです。
反論せず距離を置き、最低限の仕事しかしなくなる。そして最終的には退職...これは組織にとって大きな損失です。
「べき論」では動かない時代
では「厳しさ」をやめて「褒めるだけ」にすればよいのでしょうか。答えはノーです。
「厳しくすべき」「褒めるべき」という二元論は、価値観や背景が多様化した現代では通用しません。
本質的な課題は、リーダーの意図と部下の受け止め方の間にある「認識のギャップ」です。
成長を願ってかけた言葉が、部下には人格否定に聞こえてしまうことがあるのです。
一つのやり方が全員に通じる唯一解は存在しません。今求められるのは、一人ひとりにとっての「最適解」を探し続ける柔軟さです。
自分の「ものさし」を疑うための処方箋― 360度フィードバックという鏡
この認識のギャップを可視化し、自分の「当たり前」を見直すきっかけとなるのが 360度フィードバック です。
ほとんどの360度フィードバックは匿名で集計されるため、誰がどのような回答をしたのかは分かりません。
しかし、「自分の行動や言葉が、周囲にどのように映っているか」 を知ることはできます。
例えば、励ましているつもりの言動が、ある人には強いプレッシャーと感じられ、別の人には形式だけの声掛けだと受け取られている。
そんな多様な視点が一度に見えるのが360度フィードバックです。
360度フィードバックの価値は、誰が正しいかを判定することではありません。
むしろ、自分の一つの行動が相手によって多様な解釈をされているという“事実”を対象者(多くは管理職である上司)に突きつけるところにあります。
このデータを通じて、リーダーは、 . . . .
続きは、会員専用サイトにてご確認ください。