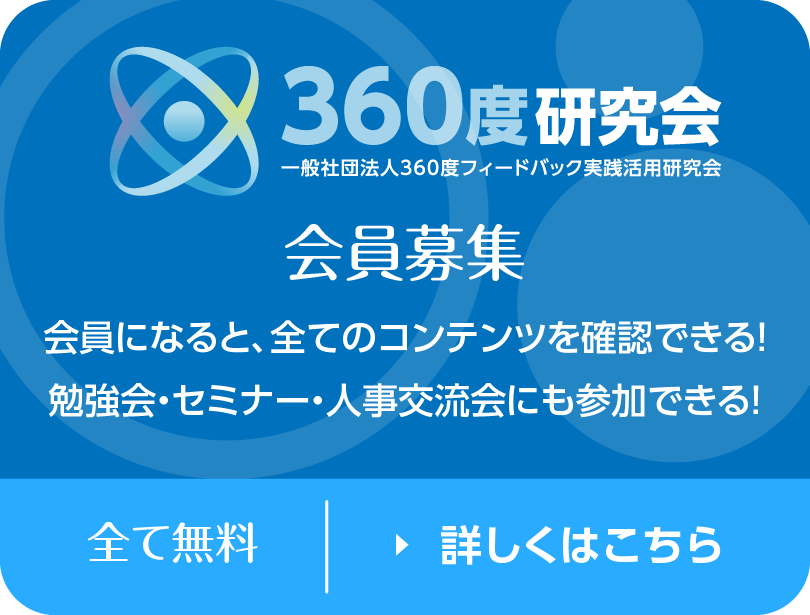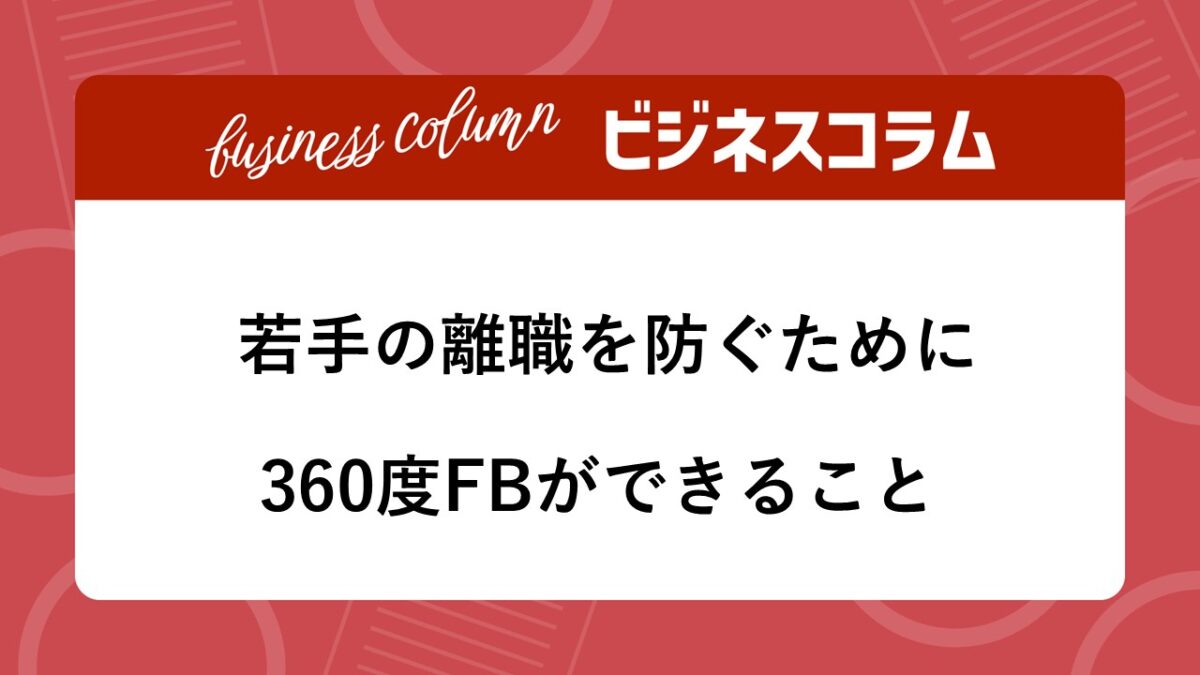
人事部の方々は、日々、人材の確保という大きな課題と向き合われていることでしょう。
厚生労働省が発表した最新の有効求人倍率(2025年8月時点)は全国平均1.20倍と、ピーク時に比べるとやや落ち着きを見せているものの、依然として1倍を大きく上回る水準にあります。
多大な時間とコストをかけてインターンシップや選考会を実施し、ようやく採用にこぎつけた期待の新人たち。しかし、その一方で、彼らが数年もしないうちに会社を去ってしまうという現実に頭を悩ませてはいないでしょうか。
これは、まるで「穴の空いたバケツ」に必死で水を注ぎ続けているような状態です。
次々と水を注ぎ込む「採用活動」にばかり追われ、そもそも水が漏れ出している「穴」、つまり「離職の原因」から目をそむけていては、いつまで経ってもバケツが満たされることはありません。
今、私たちは、採用という「入口」の対策だけではなく、離職を防ぎ、社員が長く活躍できる環境を整える「内部」の課題、すなわち「人材定着」についてもより注目すべきでしょう。
若手が会社を去る、本当の理由
退職理由として最も多かったのは「労働環境(労働時間)が良くない(25.0%)」であり、その次は「給与水準に満足できない(18.4%)」となっています。両者は、簡単に変更することが難しい問題でもあります。
ここで注目すべきは、その次に多かった「職場の人間関係が良くない(14.5%)」と「上司と合わない(14.5%)」です。「職場の人間関係」は、上司のマネジメントによってある程度改善できることを考えると、「上司」が退職に大きな影響を及ぼしていることがわかります。
更に、転職サイト「リクナビNEXT」が実施した「転職理由の “本音” ランキング」調査(2017年に公開)では、退職理由の第1位は「上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった」という結果になっています。
多くの若手は会社の事業やビジョンに対する不満よりも、「この上司の下では、自分は成長できない」「この人のやり方にはついていけない」と感じた時、会社を去るという決断を下しているのです。直属の上司との関係性が、若手の定着を左右する極めて重要な鍵を握っていることが分かります。
なぜ、すれ違いは生まれるのか?~多忙な管理職の現実~
離職の原因が「上司」にあると聞くと、管理職の能力不足を責める声が聞こえてきそうですが、事態はそう単純ではありません。 今日の管理職の多くは、自身の目標数字も抱えながら部下のマネジメントも行う、いわゆる「プレイングマネージャー」です。管理職に昇進したものの、プレイヤー業務は引き続き継続している(しなければならない)方が多い状況にあります。
そのため、昇進直後から自分のプレイング業務に追われ、部下一人ひとりと丁寧に向き合う時間的・精神的な余裕がありません。
部下を育成したいという想いはありながらも、具体的に何をどうすれば良いのか分からず、つい過去の自分の経験則に基づいた一方的な指導になってしまう。
そんな苦悩を抱える管理職は、決して少なくありません . . . . .
続きは、会員専用サイトにてご確認ください。