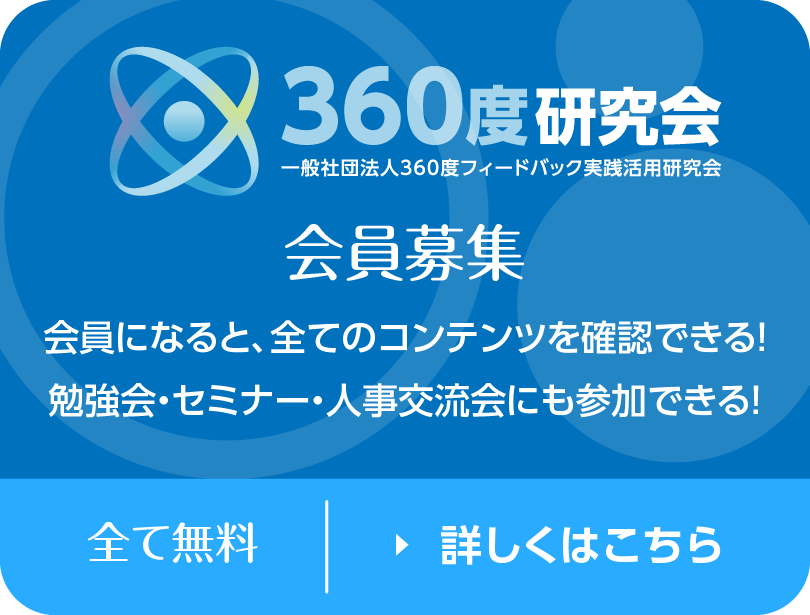-1200x675.jpg)
基本的な定義
様々な表現で定義されますが、ここでは「上司・同僚・部下、関係者など周囲の人達が、対象者の日常の行動を観察してアンケート回答し、その結果を整理して本人にフィードバックする仕組み」と表現します。360度フィードバックを実施することで、自分の行動が周囲の人達にどのように伝わっているのかを気づかせ、必要な行動改善を促すことができる手法であると言えます。
ネーミングに込めた思い
1990年代は「多面評価」「多面観察評価」と呼ばれることも多くありましたが、一般的には「360度評価」という名称で呼ばれています。
ただ、「360度評価」の「評価」という表現によって、「評価≒査定」といったネガティブなイメージを持たれてしまい、「部下から上司への逆査定」という誤解を生じることも少なくありません。
近年は、本人へのフィードバックを通じて人材育成につなげる活用が多いこともあり、「360度フィードバック」と呼ばれることが増えています。もちろん評価を目的とした活用もあり、本研究会の中でも評価手法としての活用方法も解説します。
本研究会では、この手法の本質的な価値である「フィードバック」を軸として考え、「360度評価」も含めたた上で「360度フィードバック」を考えていくこととします。
360度フィードバックはいつ生まれたのか?
1940年代の第二次世界大戦中に英国で実施されたのがスタートであると言われています。海外に派遣する諜報員の選定の際に、適任者を多数の評価者が評価するというものだったようです。「映画007の主人公を選定するといったイメージ」ではないかと思われます。
その後、1950年代に米国の軍隊(兵学校)で同様の使われ方をし、継続的な研究結果によってリーダーシップの診断に使われるようになりました。
企業で活用され始めたのは1960年代のようですが、当時は、人の評価ではなく、職務に対する評価(職務給決定のための職務価値の測定)であったようです。
そして、1970年代から管理職の選定に使われるようになりました。
日本での活用は、米国と同様に1970年頃から人事評価を目的に神戸製鋼などで導入されました。
IHIなどではリーダーシップ研修の中で活用され、話題となったようです。
日本における普及状況(推測値)
2000年ごろの導入率は様々な調査によって調査結果は異なりますが、従業員数が500名以上の会社では10%程度であったように推測されます。
2025年の導入率も調査結果によって大きく異なりますが、従業員が500名以上の会社では概ね20~30%程度ではないかと推測されます。この25年間で大きく増えています。なお大手企業の導入率が高く、中堅・中小企業においては、まだまだこれから導入検討という状況になっています。
とはいえ、米国企業における導入率は、日本の倍以上という調査結果が見られており、日本においてはまだまだ発展の余地が大きいと言えます。
徐々にではあるが、何故普及してきたのか?
「部下から上司への逆査定」といった査定ツールとしてのイメージが先行したこともあり、多くの企業において導入に対して大きな抵抗が生じました。
しかし、人材育成手法としての活用が進んだことで抵抗感が軽減されたこと。そして何よりも、影響力がある大企業への導入が進み、成功事例が生まれたことから安心感が高まり、導入に対して前向きな企業が徐々に増えてきたことも普及の背景の一つと言えるでしょう。