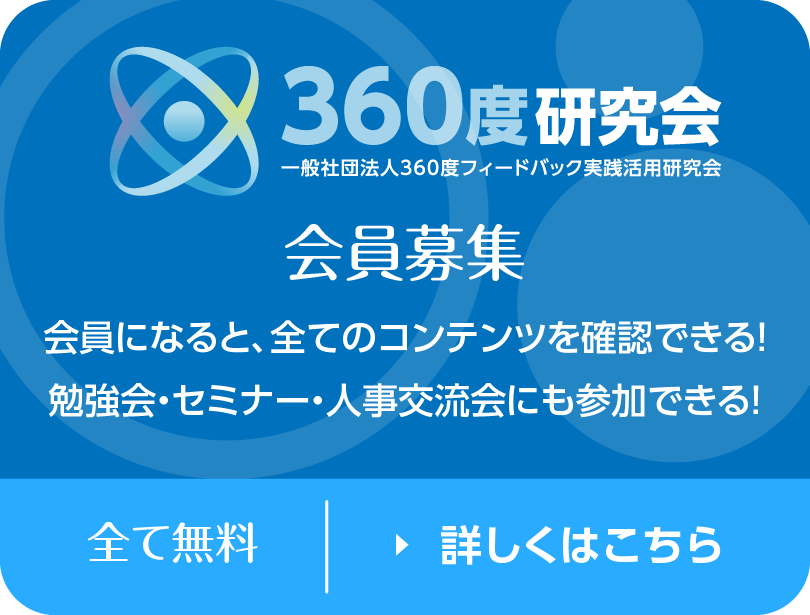コメント欄が沈黙するとき、組織は何を失っているか
360度フィードバックを導入した多くの企業で、よく耳にする悩みがあります。
それは、フリーコメント欄が空白であったり、「特になし」といった一言だけで終わってしまうケースです。
ある会社の人事部長は、この状態を「沈黙のフィードバック」と呼んでいました。
これは単に「面倒くさいから書かない」という話に見えるかもしれません。
しかし、その背景には「相手への関心の低下」や「信頼関係の希薄化」が隠れている場合があります。
コメントが書かれないという事実は、組織内のコミュニケーションの温度が下がり、血流が滞っているサインかもしれないのです。
「コメント必須化」という一時的な対策の限界
コメントが少ないなら、サーベイ回答システムでフリーコメント回答を必須設定にすればよい。そう考える企業も多くあります。
そのことで確かにコメントの量は増えるかもしれませんが、それは「義務感」から絞り出された言葉であり、本質的な成長や気づきにつながらない内容も少なくありません。
むしろ「強制された」というネガティブな印象が残り、360度フィードバックそのものへの信頼を損なう危険性もあります。
重要なのは「どうやって書かせるか」ではなく、「どうすれば自然に書きたくなるか」という視点です。
質の高いコメントを生む「土壌」とは
心のこもったコメントは、次の3つの条件が揃ったときに生まれます。
1)心理的安全性
「この内容を書いても不利益にならない」という安心感。フィードバックは単なる
批判ではなく、対象者の成長のためのものだという理解
2)貢献意識
記入したコメントは、結果として組織全体を良くすることにもつながるという意識
3)日頃の信頼関係
普段から関心を持ち、信頼を築いている相手だからこそ、真剣に言葉を届けたく
なる気持ち
これらの要素が欠けた状態でコメント数だけを増やそうとしても、質は伴いません。
「利他」が「自分ごと」になる仕組み ~成功事例から学ぶ~
多くの社員にとって、フィードバックは「相手のための行為」に見えがちです。 そこである企業では、発想を転換しました . . . . .
続きは、会員専用サイトにてご確認ください。